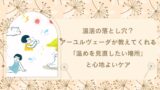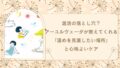はじめに|体を温めることの大切さと伝統的な知恵
私たち日本人は昔から「冷えは万病のもと」と言われ
体を温めることを大切にしてきました。
一方、インドの伝統医学であるアーユルヴェーダでは、
「どの部位を」「いつ温めるか」に細やかな配慮があります。
この記事では、アーユルヴェーダの視点を参考に、
温めると心地よいポイントや注意点をご紹介します。
※医療行為ではなく、
伝統的なセルフケアの一例としてお楽しみください。
温めて心地よいとされる部位
1. 足もと
- 足は冷えを感じやすい場所の一つです。
- アーユルヴェーダでは、夜に頭部に熱が集まりやすいとされ、
足を温めることで熱のバランスが整いやすいと伝えられています。
おすすめセルフケア
- ぬるめの足湯を10分程度
- 天然素材の靴下を履く
2. 仙骨(せんこつ)
- 仙骨は骨盤の中央に位置し、
体の中心にあたる重要な場所です。 - 温めることで骨盤周りの巡りがよくなり、
リラックスを促すとされています。
おすすめセルフケア
- 小さめの湯たんぽで優しく温める
- 軽い腰回しストレッチを取り入れる
3. お腹(特に胃腸周辺)
- アーユルヴェーダでは
消化の火「アグニ」が健康の鍵とされ、
お腹を温めることが消化のサポートにつながると考えられています。 - ただし、食後すぐの温めは避け、
空腹時や冷えを感じるときに行うのがおすすめです。
おすすめセルフケア
- ぬるめの白湯をゆっくり飲む
- 薄手の腹巻きを利用する
温める際の注意点
- 頭や目などは冷やすことが心地よい場合もあるため、
全身を温めれば良いとは限りません。 - 自分の体調や季節に合わせて、
心地よく感じる範囲で調整してください。 - これは医療行為ではなく、伝統的な健康法の一つです。
まとめ|自分に合った温め方で心身の調和を
アーユルヴェーダの知恵を活かし、
足もと・仙骨・お腹を
自分の状態に合わせてそっと温めることで、
より快適な日々を過ごせるかもしれません。
ぜひ無理なく続けられる
セルフケアとして取り入れてみてください。
実際、以前の記事では
- 頭や目は温めるよりも冷やしたほうがいい
といった内容もご紹介しました。
気になる方はぜひ合わせて読んでみてくださいね。
👉 温めを控えたい場所の記事はこちら
温活の落とし穴?アーユルヴェーダが教える「温めを控えたい場所」とセルフケアのコツ
おわりに
体を温めるケアは簡単そうに見えて、
実はとても奥深いもの。
自分の体調や季節に合わせて、
足もと・仙骨・お腹をそっと温める
時間をつくってみてはいかがでしょうか。
アーユルヴェーダ的な養生を、
日々の暮らしに少しずつ
取り入れてみるのも良いかもしれません。
今日も読んでくださりありがとうございました!!