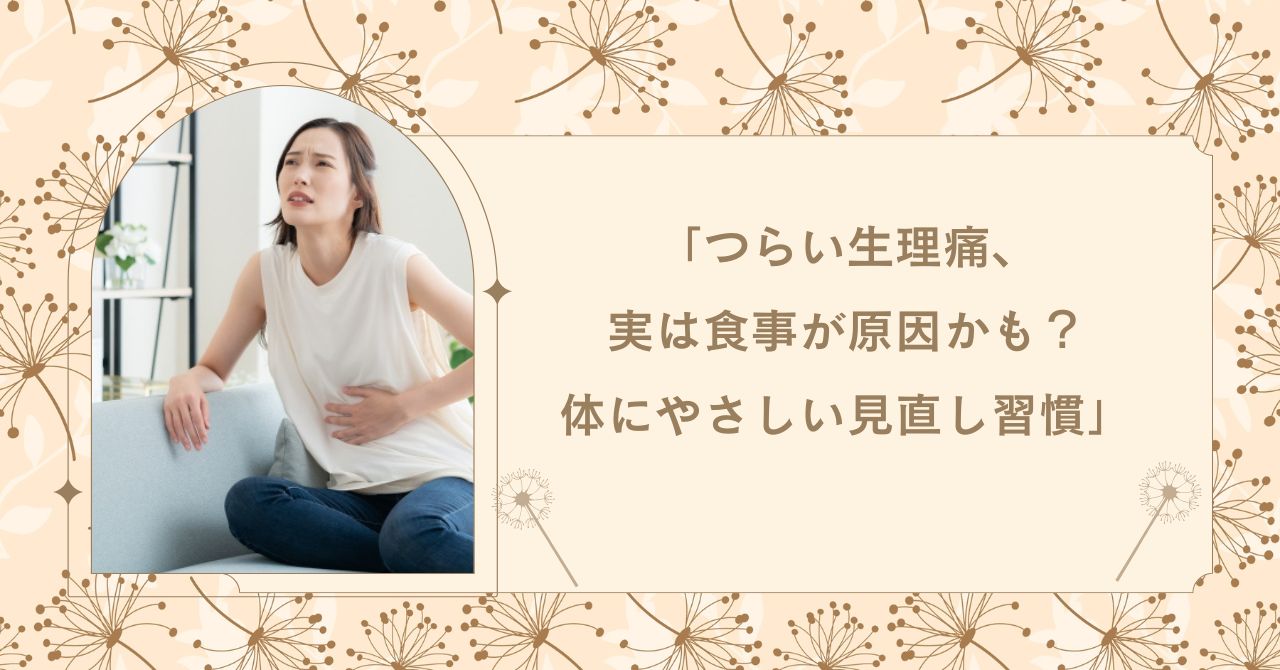はじめに
「生理痛はひどくて当たり前」
と思っていませんか?
毎月、鎮痛剤が手放せず、
仕事や家事に集中できない。
夜用ナプキンが昼間も必要になるほど経血が多い。
血の塊が出たり、刺すような痛みを感じる。
そうした悩みを「女性だから仕方がない」
と諦めてしまっている方も多いのではないでしょうか?
実は最近、
「生理痛の背景には食事や生活習慣が
大きく関わっているのでは」
という声も増えています。
この記事では、医師であり分子栄養学に詳しい
吉野敏明氏が発信する内容を参考に、
生理痛やホルモンバランス
のヒントになる情報をまとめました。
「薬に頼る前に、まずは毎日の暮らしを見直す」
という選択肢のひとつとしてお読みください。
生理の仕組みをもう一度
女性の体は月に一度、
妊娠に備えて子宮内膜が厚くなり、
妊娠が成立しなかった場合にその内膜が剥がれ落ち、
血液とともに排出されます。
これが生理(月経)です。
ホルモンや自律神経、血流が複雑に連動するこのサイクルは、
食事やストレス、生活習慣の影響を大きく受けると言われています。
吉野敏明氏が語る「油と子宮」の話
吉野氏は、生理痛の一因として
植物性油(特にリノール酸やオメガ6系脂肪酸)
の過剰摂取に注意を呼びかけています。
これらはサラダ油や大豆油、外食やスナック菓子などに多く含まれ、
酸化しやすく体内で炎症を招きやすいとされます。
また、血流が滞ると子宮内膜がスムーズに排出されず、
体がそれを押し出そうとして
子宮を強く収縮させることで痛みが強まる場合もあるそうです。
ただし、これらは吉野氏の臨床経験に基づく見解の一つであり、
すべての人に当てはまるものではありません。
ホルモンバランスと乳製品・大豆製品
乳製品に含まれる「外因性エストロゲン」や、
大豆製品に含まれる「大豆イソフラボン」は、
女性ホルモンのバランスに影響を与える可能性が指摘されています。
特に思春期や生理前のデリケートな時期は、
ホルモンの変動が起こりやすいもの。
吉野氏は
「体調や時期を見ながら、
摂取量に注意を払うことも一つの方法」と話しています。
現代の生活とホルモンリズム
ブルーライト(スマホやPC)によって松果体が刺激され、
メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌が乱れることで
ホルモン全体のリズムに影響が出ることもあると言われます。
夜はなるべくブルーライトを避けて、
朝にしっかり太陽の光を浴びることで体内時計を整える習慣は、
生理周期だけでなく全身の健康にもつながる大切なポイントです。
動物性脂肪とホルモンの材料
一方で、極端な脂質制限や動物性脂肪の不足が
ホルモン合成に影響し、
生理が止まる(無月経)リスクを高めるという見解もあります。
コレステロールはホルモンの材料でもあるため、
バランスよく良質な脂質を摂ることも検討したいところです。
まとめ:小さな選択が体を変えていく
生理痛は「女性だから仕方がない」
と我慢するものではなく、
体の声を聴く大切なサインかもしれません。
食事や生活環境を見直すことは
すぐに大きな変化を感じるものではないかもしれませんが、
少しずつ体が整っていくきっかけになる可能性があります。
免責事項
当サイトの記事は、健康や栄養に関する一般的な情報や筆者の見解を紹介するものであり、
医学的診断や治療を目的としたものではありません。
体調や心身に不調を感じた場合は、必ず医療機関や専門家にご相談ください。