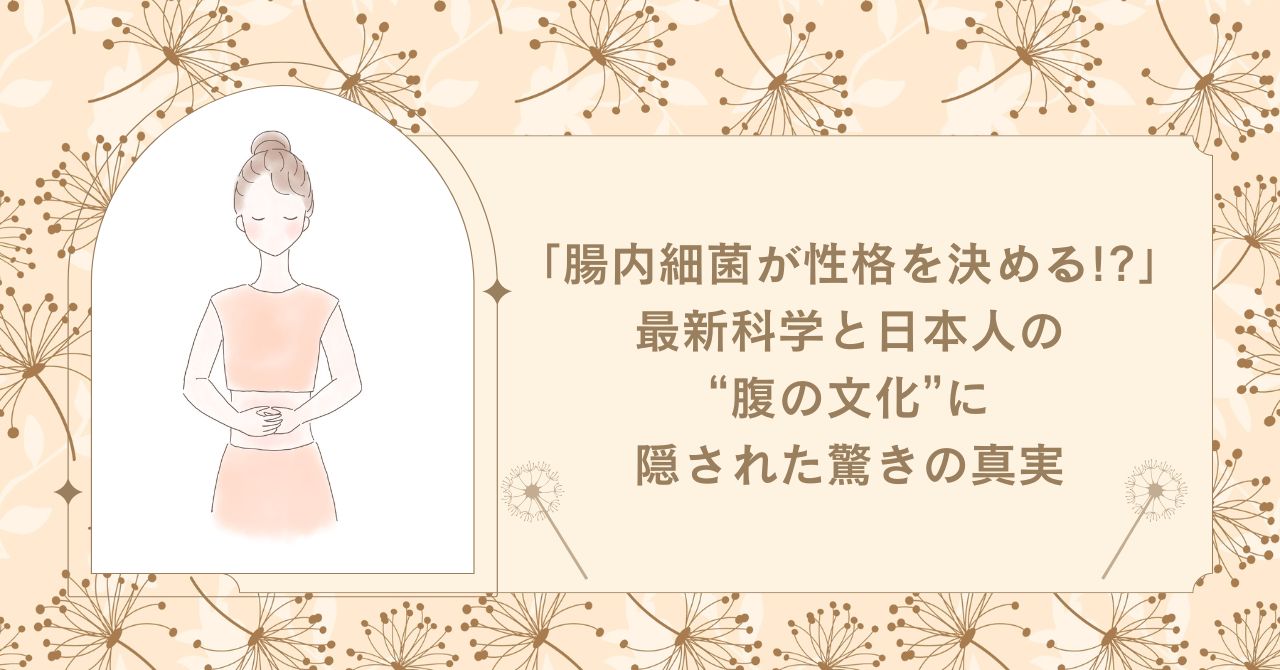「腹が立つ」「腹を割る」「腹を据える」─
─日本語には、
腹を通して感情や意志を表現する言葉
が数多くあります。
一見、比喩のようにも思えますが、
実はこの“腹”という感覚は、
科学的にも精神的にも、
私たちの本質を表しているのかもしれません。
今回は、
「腸内微生物=性格や意思を形づくる存在」
という観点から、
日本人の精神文化や食習慣と
つながる深い世界に触れてみたいと思います。
腸は「第二の脳」──感情は腸から生まれている?
私たちの腸には、
約1億個もの神経細胞が存在すると言われています。
これは脳の次に多く、
腸が自律的に考え、感じている
とも言えるほどの構造です。
このことから
腸は「第二の脳(セカンドブレイン)」と呼ばれ、
最新の神経科学では、
腸がセロトニン(幸福ホルモン)
の90%以上を生成している
こともわかっています。
つまり、
「幸せ」「安心」「やる気」「気分の落ち込み」
などの感情は、
実は腸で決まっているとも言えるのです。
微生物があなたの性格を左右する?
腸内に棲む100兆個以上の腸内細菌たち
(マイクロバイオータ)は、
消化吸収を助けるだけでなく、
神経伝達物質の合成、免疫系の調整、
さらには脳の意思決定や感情反応にまで
影響を与えることが、
近年の研究で明らかになってきました。
たとえば、
以下のようなことがわかっています。
- 特定の菌が多い人は、社交的で前向き
- 別の菌が優勢な人は、内向的で不安になりやすい
- 動物実験では、腸内環境を移植すると性格も変化する
つまり、
私たちの「心の状態」や「性格」は、
腸内に住む微生物の構成に
左右されているということなのです。
日本人の腸は、他の民族と違う?
特に日本人の腸内環境は、
世界的に見ても特異な構成を
持っていることがわかっています。
それは、日本の伝統的な食生活─
─味噌、納豆、漬物、ぬか漬け、海藻、
発酵食品などが豊富に含まれていたからです。
中でも興味深いのが、
海苔に含まれる「ポルフィラン」
という多糖類を分解できる特殊な腸内細菌が、
日本人だけに見つかったという研究
(2005年、フランスのピエール・ブトン氏
による発表)です。
これは、長年にわたる食習慣が
腸内細菌を進化させたことを意味します。
つまり、日本人の体内には、
日本独自の微生物たちが共生しており、
彼らが日本人の精神性や行動特性を
一部つくっている可能性があるのです。
腸内微生物は“共生しているもう一人の自分”
このように腸内細菌は、
自分の外にあるようで、
限りなく「内なる自分」に近い存在です。
彼らは食べ物から栄養を取り、
私たちに恩恵
(神経伝達物質、免疫調整など)をもたらし、
日々私たちと会話を交わすように
影響を与えています。
スピリチュアルな視点から見れば、
腸内微生物はまさに
「目に見えない魂の仲間たち」
とも言えるでしょう。
それはアニミズム的な日本人の精神観─
─森羅万象に命が宿るという
感性にも通じています。
「腹に宿る魂」──丹田と和の精神
武道や禅、茶道、能など、
日本の伝統文化においては、
「丹田(たんでん)に意識を置く」
ことが極めて重視されます。
丹田はへその下にある
エネルギーの中心であり、
身体の軸、精神の安定、決断の核心
を担う場所とされてきました。
これも単なる精神論ではなく、
腹部(腸)と精神のつながりを
無意識に理解していた証拠
とも言えるのではないでしょうか。
日本語においても、
- 腹が立つ
- 腹をくくる
- 腹を決める
- 腹を読まれる
など、腹=感情・意思・直観の宿る場所として、
今も日常の中に生き続けています。
終わりに──微生物が教えてくれる「本当の自分」
私たちはつい、
自分の感情や性格を
「脳の働き」だと思いがちです。
しかし、科学とスピリチュアルの
双方の視点を融合させて見ると、
「自分」とは
腸内で共に生きる微生物たち
との共同体である
とも言えるのです。
今、世界中で「腸活」が注目されているのも、
単なる健康トレンドではなく、
人類が“内なる生命”の存在に
気づき始めたサインなのかもしれません。
これからの時代は、
腸と心をつなぎ、
微生物たちとの共生意識を持つことが、
本当の自己理解と調和への鍵になるでしょう。
あなたの“腹の声”に、耳をすませてみませんか?